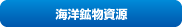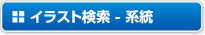イラスト検索
船>海洋
海には食料資源としての魚がすんでおり、その魚を捕獲する目的の船が漁船です。カツオやイカなどの釣漁船、サケやマスの流網漁船、マグロの延縄漁船、カレイやタラのトロール漁船など様々です。
海洋には様々な環境が存在し、海洋の温度や流速を調べたり、海底の地形や資源を調べる探査もあります。上空から調べる場合もあれば、海洋表面、海洋中で調べる場合もあります。特に深海の状況を調べるために「しんかい」や「かいこう」などの海洋探査機が実用されています。
海底には様々な鉱物資源が眠っています。日本は海洋に囲まれており、沿岸から200海里で定義される排他的経済水域の面積は広大であり、水産資源のみならず海底には石油や希少鉱物など経済的に有益な資源が多くあります。
水中に超音波を発信し、それが物体に当たって戻ってくる音波を検出することによって魚の群れを発見する装置を魚群探知機と言います。もとはソナーと呼ばれる軍事用の水中探査技術であるが、今日では水深測定や魚群探知など平和利用が増えてきています。