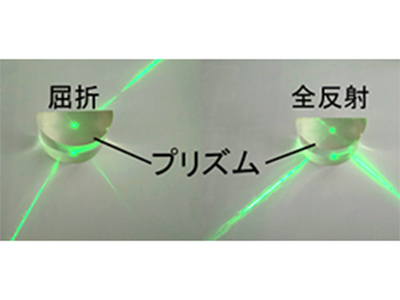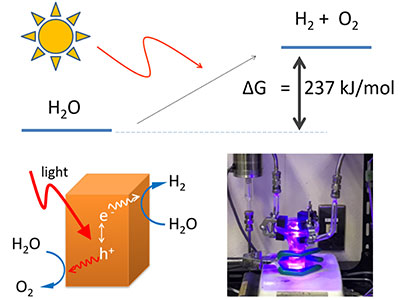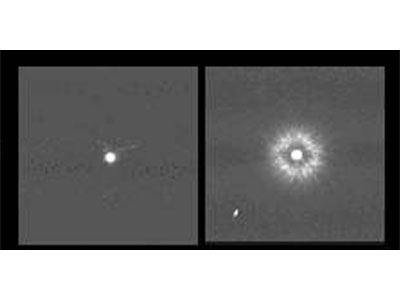環境への取り組み
魚類残渣からの再資源材料の開発と環境問題への応用
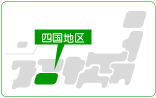
2025年1月17日
四国地区
香川大学 創造工学部
教授 吉田秀典
研究の背景
筆者が教育・研究の拠点としている香川県は、風光明媚な瀬戸内海を擁し、同時に、海から水産資源、歴史・文化・芸術を享受し、さらに、海は大量の炭酸ガスを吸収(ブルーカーボン)することから、まさに、瀬戸内海は自然が生み出した「宝庫」です。しかしながら、瀬戸内海では、コンクリート骨材や海面埋め立て資材として大量の海砂が採取され、水産資源や自然環境への深刻な影響をもたらしました。さらに、瀬戸内海に浮かぶ美しい島の1つである豊島には、昭和50年代後半から平成2年にかけて大量の産業廃棄物が搬入・不法投棄され、土壌や地下水は有害物質に汚染されました。こうしたことを受け、筆者は、SDGsが提唱される以前より、瀬戸内海の環境回復と持続可能な社会の実現に向け活動をはじめ、手始めに、廃棄物の大幅な減容を目途として、水産加工の際に廃棄される魚骨を再資源化するという研究を開始しました。その研究成果の1つが、魚骨由来のヒドロキシアパタイト(Fishbone Absorber、特許番号6351008、以降FbA)の開発です。
研究のポイント
廃棄物の再資源化
FbAについては、食品加工廃棄物として廃棄される予定の魚類残渣(写真1参照)より製造され、熱を加えるのみで残渣等を落とすことができることから、工場製造のヒドロキシアパタイトと比べ、圧倒的に低コストで製造が可能です(写真2参照)。また、FbAは家畜由来のヒドロキシアパタイトと異なり、狂牛病、豚熱インフルエンザや鳥インフルエンザと言った病原体についてはフリーで、生体親和性に優れ、さらに、ヒンズー教では牛を、イスラム教では豚そしてハラル(イスラム法に従って処理された食品)以外の鶏を食せないと言うような宗教的なハードルは無く、国際展開が可能です。
 写真1 魚類残渣の例
写真1 魚類残渣の例 写真2 魚骨由来のヒドロキシアパタイト
写真2 魚骨由来のヒドロキシアパタイトFbAの特徴と環境問題の解決
FbAは各種有害物質を吸着できることから、海洋、河川、地下水などの浄化が可能であるだけでなく、カルシウムが豊富であることから、セメント代替としてコンクリートに混和が可能です。この特徴を活かし、これまでSDGsの目標6の「安全な水の確保」、目標12の「廃棄物の削減と二酸化炭素の減少」、さらには目標14の「海の豊かさを守る」という各ゴールの達成を目指しております。
「海の豊かさを守る」では、植生に不可欠なリンを含むFbAをコンクリートに混和した藻場造成用多孔質基質(写真3参照)の製造・設置し、藻場の造成と海域底質の改善(自然共生社会の実現)と、繁茂した藻場に二酸化炭素(以降、CO2)を吸収させ(低炭素社会の実現)、ブルーカーボンの実現を目指しています。また、「廃棄物の削減と二酸化炭素の減少」では、コンクリートにFbAを混和することで廃棄物を削減すると同時に、製造時に大量のCO2を排出するセメントの代替としてカルシムリッチなFbAを混和することでCO2の排出抑制(低炭素社会の実現)を目指しています。さらに、有害物質封緘機能を有するコンクリートに、有害物質を吸着したFbAを混和することで、逼迫する最終処分場問題の解決を図っているほか、FbAはリンを豊富に含むため植生用のポーラスコンクリート(写真4参照)の開発を行っています。「安全な水の確保」では、FbAを用いて、重金属の他にストロンチウム、ヒ素(図1参照、なお、ヒ素に吸着には、FbAの改良型(FFPと称する)をも用いて吸着効率を上げている)、フッ素(図2参照)の吸着を可能としており、さらに、PFAS(有機フッ素化合物)や菌類(大腸菌に代表されるたんぱく質類)の吸着を目指しております。
このように、廃棄物の再資源化など、すなわちFbAの開発を通して循環型社会を目指すと同時に、低炭素社会ならびに自然共生社会、すなわち持続可能な社会の実現に邁進しております。
 写真3 人工漁礁に繁茂した海藻の例
写真3 人工漁礁に繁茂した海藻の例 写真4 植生ポーラスコンクリートの例
写真4 植生ポーラスコンクリートの例 図1 初期濃度3mg/Lにおける24時間振蕩試験後の各重金属の残留濃度(棒上の値は溶液のpH)
図1 初期濃度3mg/Lにおける24時間振蕩試験後の各重金属の残留濃度(棒上の値は溶液のpH)
 図2 初期濃度3mg/Lにおける24時間振蕩試験後のFbAの添加量とフッ素の残留濃度の関係
図2 初期濃度3mg/Lにおける24時間振蕩試験後のFbAの添加量とフッ素の残留濃度の関係
まとめ
FbAに係る環境問題への貢献と今後の課題は、以下のようにまとめられます。
社会的価値の訴求
FbAは廃棄魚骨より製造されることから、廃棄物の低減に繋がるだけでなく、有害物質吸着後のFbAを再資源化してコンクリート/植生コンクリートへの混和することで、さらなる廃棄物の低減となることから、FbAの社会実装を通してサーキュラーエコノミーにも資する持続可能な社会を目指します。
環境負荷の低減
廃棄物の資源化、さらには有害物質吸着後のFbAの再資源化によって、廃棄物処分の際に発生するCO2を抑制するだけでなく、処分量の削減により汚染物質の漏洩リスクの低減を目指します。
安全性
FbAは、複数の重金属などのカチオン、フッ素などのアニオン、そして、FbAを水酸化鉄で被膜したものは、複数の化学種が混在する水溶液から選択的にヒ素を吸着できることから、有害・汚染物質の発生と排出抑止に貢献します。また、FbAは魚骨より製造されるので、生物・環境親和性が高いだけでなく、疫病リスクが低く、さらに、宗教的なハードルも低いので、今後は国際展開も視野に、さらなる持続可能な社会の実現を目指します。
水問題の解決
ヒ素、フッ素、PFAS (PFOS/PFOA/PFHxS)、大腸菌などによる汚染によって、世界的に飲料水問題が顕在化してます。FbAは、ヒ素、フッ素の吸着も可能であることから、今後、PFASならびに大腸菌の吸着も可能となるように研究を重ね、世界的な水問題の解決を実現します。
| 掲載大学 学部 |
香川大学 創造工学部 | 香川大学 創造工学部のページへ>> |