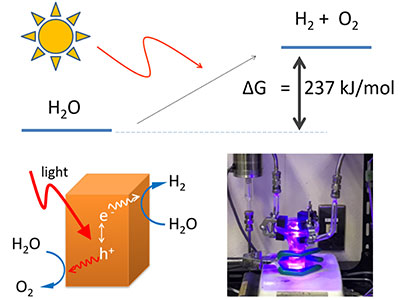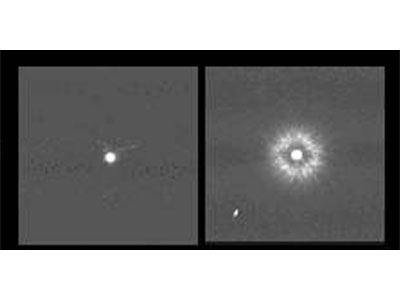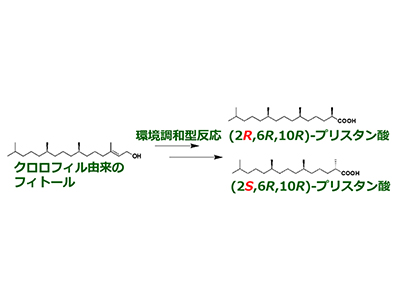環境への取り組み
ヒートポンプ熱源としての貯水池の利用

2021年12月17日
東海地区
三重大学 工学部
はじめに
化石燃料への依存度が高いわが国において、太陽光、風力、水力、地熱などの再生可能エネルギーへの転換の促進に加えて、電力等の効率的な利用が求められています。
本稿では、建築学コース環境系研究室が広島大学と共同で取り組んでいる、湖沼やため池などの貯水池をヒートポンプシステムの熱源として利用する省エネルギー技術に関する研究を紹介します。
ヒートポンプ技術と省エネルギー
ヒートポンプ技術は、低温熱源を冷却して熱を取得し、その熱をより高温の熱源に移動させて高温熱源を加熱することができる技術で、身の回りの冷蔵庫やエアコン、ヒートポンプ給湯器等で加熱と冷却のために利用されています。エアコンによる暖房(図1)では、外気(低温熱源)から熱を集めて、居室(高温熱源)に熱を供給して暖房します。このときに投入される電力エネルギーは、暖房として居室に供給される熱エネルギーの1/7~1/5程度であり、ヒートポンプ技術は電力の利用効率の高い省エネルギー技術であるといえます。
 図1 ヒートポンプの原理(エアコンによる暖房)
図1 ヒートポンプの原理(エアコンによる暖房)ヒートポンプ機器の効率は既に非常に高い水準にあり、さらなる機器効率の向上は困難な状況にあります。一方で、高温熱源と低温熱源の温度差が小さいほど、効率が高くなる特性があるので、ヒートポンプの熱源として一般に利用される大気と比較して、夏季に温度が低く冬季に温度が高くなる、地盤や地下水、河川水、海水等を暖房時の低温熱源(ヒートソース)・冷房時の高温熱源(ヒートシンク)として利用することで、省エネルギーが図られています。
ヒートシンクとしての貯水池利用
貯水池の温度分布
ヒートポンプの熱源として、湖沼等の貯水池水を利用するにあたって、その水温はヒートポンプの効率を左右する重要な因子です。図2は、貯水池水の鉛直方向の温度分布を示しています。これは広島県東広島市のため池で測定された結果です。春から夏にかけて、気温の上昇や日射量の増大によって、貯水池上部の水温が上昇します。水は温度が高いほど密度が低くなり、浮力ために上部に滞留します。風などによって撹拌もされますが、夏季には水深が深くなるに従って温度が低下する温度分布が形成されます。このように、夏季(8月1日)には貯水池底部の水温(水深5m、14.7℃)が平均外気温度(26.7℃)に比べて低く保たれています。一方、秋から冬にかけては、水面が冷却され、対流によって底部まで冷却されるため、水面から底までほぼ同じ温度となり、それ以降は一様に温度が低下していきます。4℃以下では温度が低下するほど密度が低くなるので、水温低下や凍結は水面付近に限られ、貯水池全体の水温が4℃を下回ることはありません。
 図2 貯水池の水温分布の年変動(2013年)
図2 貯水池の水温分布の年変動(2013年)このように温暖地域で、夏季の冷房期間に貯水池底部の水温が外気温よりも低く保たれる場合には、貯水池水をヒートポンプのヒートシンク(冷房時の高温熱源)として利用することで、冷房用電力の削減が期待されます。一方、ヒートソース(暖房時の低温熱源)としての利用の効果は、寒冷な地域に限られると考えられます。
貯水池水をヒートシンクとして利用したときのシミュレーション
貯水池水をヒートシンクとして利用したときの水温分布や省エネルギー効果について検討するために、貯水池の日射吸収や水分の蒸発・凝縮、水中での熱拡散、貯水池への放熱等を考慮した簡易な鉛直一次元拡散モデルを用いています。図3は実測した東広島市のため池の水温をその年の気象条件を用いて計算した結果を示しています。計算結果は実測結果とよく一致しているわけではありませんが、春から夏にかけて貯水池上部の温度が上昇し、底部が低温に保たれる傾向は再現できています。
 図3 貯水池の水温分布の計算結果と実測結果の比較
図3 貯水池の水温分布の計算結果と実測結果の比較このモデルを使用して、貯水池水をヒートポンプのヒートシンクとして利用した場合の貯水池水の水温予測や省エネルギー効果等の検討を行っています。図4に計算結果の一例を示します。ここでは、貯水池の底部から低温水を取水し、ヒートポンプの凝縮器を冷却して温度上昇(+5℃)した水を貯水池の中間の高さに戻すという条件で計算しています。点線で示した自然の水温と比べて、冷房期間の底部の水温が高くなっているのがわかります。この温度差に比例する熱量を貯水池に放熱しています。その後、秋から冬にかけて貯水池水温は低下し、自然水温と同じ4℃程度の水温に戻ります。冷却塔という装置を使って大気を熱源とする場合と比較して、貯水池水温が低いため、この計算例では、ヒートポンプの電力消費量を37%程度低減できることになりました。
 図4 貯水池水をヒートポンプのヒートシンクとして利用したときの水温の計算結果
図4 貯水池水をヒートポンプのヒートシンクとして利用したときの水温の計算結果おわりに
貯水池水の熱源利用による省エネルギー技術について紹介しました。貯水池のヒートシンクとしての利用することで、大気を利用する場合と比較してヒートポンプの消費電力の削減が期待できることがわかりました。実際に利用するためには、貯水池の利権や環境影響等の問題が残っていますが、今後機会があれば実証実験を行いたいと考えています。
| 掲載大学 学部 |
三重大学 工学部 | 三重大学 工学部のページへ>> |