生レポート!大学教授の声
異分野融合研究を成功させるためには
豊橋技術科学大学 電気・電子情報工学系
澤田 和明
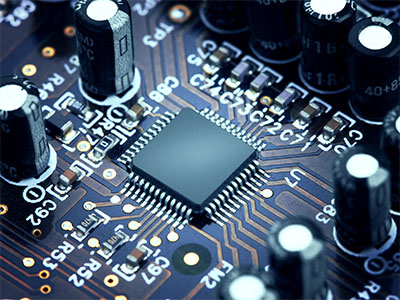
最近異分野連携研究、融合研究の重要性が異口同音に言われている。しかしながら、異分野の研究者との融合研究は、専門用語の違いや研究展開の考え方など違いが大きく、苦労された経験をされた方も多いのではないだろうか。本稿ではこれまで筆者が行ってきた医学・生命科学分野研究者との異分野連携研究を紹介し、これから融合研究を進める方々の参考になればと思い筆をとった。
筆者は集積回路技術をベースとしたセンサデバイスの研究・開発を専門分野としている。現在開発を進めているセンサに、“イオンイメージセンサ”というものがある。水中で対象物のイオンの挙動を直接に観察するものである。世界中を探してもこのようなセンサは実在していなかったが、自前で様々な集積回路を作ることができる豊橋技術科学大学にある“LSI製造設備”で開発に成功することができた。生命科学・医学分野の研究者に使っていただきたかったところ、あるきっかけで医学部の先生から共同研究のお誘いを受けた。大学の設備で作製した、できたてのセンサを3個持参したところ、それでは使いづらいということであった。医学系の研究は、再現性を取るために何度も測定する必要があるため、精度がそろった大量センサが必要なことや、電気回路に不慣れな研究者がその回路を動かさないといけないことがその原因であった。製作したチップが医学の環境で動くか否かのチェックであれば数個で十分だが、医学系の先生がそのチップを活用し世界で初めてのデータを世の中に出すためには、大量に必要とされた。それから我々は、再現性良く1000個単位でセンサが提供できる体制と、専門外の方も簡単なソフトウェア操作でイオンのイメージングができる装置を5年もの歳月をかけて開発した。その成果により、現在では工学部とは異なる21もの国研、大学、企業などと異分野連携研究が進めることができている。いったん、共同研究者から信頼を得ることができると、次の用途の相談や新たな開発の要望を聞くことができるようになり、現在では新たなセンサ研究開発という充実した連携研究に発展している。
世界に実在していないものを異分野の方に使っていただくためには、上記のように、異分野の研究者の状況を理解して、歳月や苦労を伴うものの、共同研究のために必要な環境を構築していなかったら、このような連携研究には発展できなかったと感じている。
| 掲載大学 学部 |
豊橋技術科学大学 | 豊橋技術科学大学のページへ>> |
関連記事
(>>会員用ページ)
| 私たちが考える未来/地球を救う科学技術の定義 | 現在、環境問題や枯渇資源問題など、さまざまな問題に直面しています。 これまでもわたしたちの生活を身近に支えてきた”工学” が、これから直面する問題を解決するために重要な役割を担っていると考えます。 |








