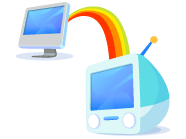生レポート!卒業生の声
小さな興味から拡がる世界
新潟大学工学部
自然科学研究科電気情報工学専攻
東京農工大学 T.S.
私は現在、東京農工大学の産学官連携研究員として国立天文台との共同研究である系外惑星探査観測装置の保守・開発に携わっています。天文学では大きな問いの一つである太陽系の外に「地球のような星は存在するのか」、その解明に向けた観測や調査が進んでいます。一見すると工学と天文学は異なる分野ですが、惑星観測装置の根幹には工学の知識が不可欠で大学での学びが今も現場で活かされています。
工学部と聞くと「ものづくり=機械を作る」という印象が強いかもしれません。しかし装置やシステムの仕組みを理解し想定通りに動作させる技術力を養うことも工学部ならではの強みです。実際に私が関わった装置が天文学者に利用され、惑星観測や新たな系外惑星の発見につながった経験は、研究の規模の大きさと現場での達成感を肌で感じる貴重な機会となっています。
1. 工学部を選んだきっかけ
私が工学部を選んだ理由は高専のオープンキャンパスで「なぜ電気で光を研究するのか?」という疑問を抱いたことがきっかけでした。この小さな疑問から大学では工学部に進学し、光計測分野の研究室に所属しました。
研究活動の中でレーザ光源の駆動回路や干渉計の組み立て、光信号処理のプログラミングなど、自分の手で装置を構成する中で理解が深まりました。また装置全体は光源制御・光学系・信号解析といった多様な技術の組み合わせで成り立つことや基礎原理の理解が重要であることを学びました。
2. 学生時代の経験が活きる場面
現職でもこれらの経験が直結しています。例えば天文観測装置は夜間に無人で稼働するためリモート制御が欠かせず、学生時代のプログラミング経験は制御ソフト理解の大きな助けとなりました。さらに光学製品の扱いや基礎特性の確認経験は装置状態の把握やトラブル対応、修理・交換作業に直結し装置の安定運用に欠かせません。
3. 最後に工学部を目指す皆さんへ
私自身、大学入学や在学中に明確な目標があったわけではありません。しかし、ちょっとした疑問や興味をきっかけに今では最先端装置に触れ異分野をつなぐ研究に関わることができています。身近な疑問に目を向け、試行錯誤して理解や解決に至る経験は必ず将来に活かせますので、ぜひ「ちょっと気になる」「やってみたい」と思うことに挑戦し、工学部でしか得られない学びの広がりを体験してみてください。
 すばる望遠鏡 外観写真
すばる望遠鏡 外観写真 系外惑星探査装置
系外惑星探査装置| 掲載大学 学部 |
新潟大学 工学部 | 新潟大学 工学部のページへ>> |