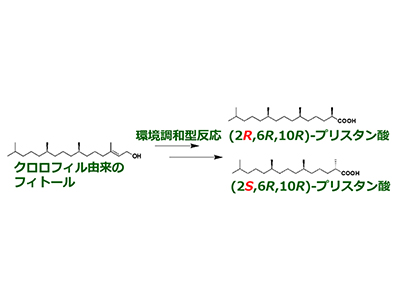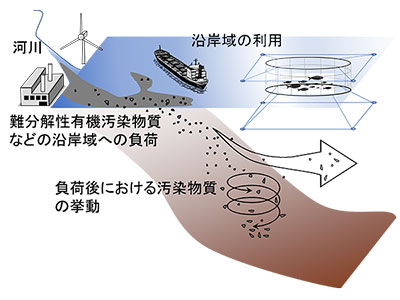生レポート!大学教授の声
工学部で学ぶということ
長崎大学
社会環境デザイン工学コース
中村 聖三
 史跡保護のため片側(手前側)のみで支えられた「出島表門橋」
史跡保護のため片側(手前側)のみで支えられた「出島表門橋」皆さんは「工学部」は何を学ぶところだと思っていますか?「理学部」との違いは何でしょうか?
手元にある広辞苑で「工学」を調べてみると、「基礎科学を工業生産に応用して生産力を向上させるための応用的科学技術の総称」と書かれています。一方「理学」は「自然科学の基礎研究諸分野の称」と説明されています。「理学」が基礎的な”研究”分野であるのに対し、「工学」は応用的科学”技術”であるという説明だと理解できそうです。私自身は「理学」が自然の理(ことわり)、すなわち真実を追求する学問であるのに対し、「工学」は人々の暮らしをより安全に、快適に、便利にする”モノ”や”環境”を作り出す学問であると考えています。
「工学部」は言うまでもなく「工学」を学ぶところです。高校で学ぶ科目の中では「数学」や「理科(特に物理)」が基礎になります。高校時代はこれらの科目を「何のために学ぶのか」、「社会に出てから使うことがあるのか」といった疑問を持つ人が多いのではないでしょうか。しかし、「工学」では「数学」や「理科」の知識は間違いなく必要です。現実の問題を解決したり、新たなモノづくりをするために利用します。例えば、私の専門分野である土木工学では様々な公共構造物を設計します。その代表格である橋には、自動車の重さや地震などの外力が作用しますが、それらに耐え安全に利用できることが求められます。それを実現するためには、物理(特に力学)の知識が必要です。力のつり合いや運動方程式などが用いられます。運動方程式は本来微分方程式ですので、それを解くために数学の知識も必要です。
工学部でも、入学当初は「数学」や「物理」など、高校の延長のような勉強をします。しかしそこには、モノや環境を改善したり新たに作り出すのに用いるという明確な目的がある点が、高校での学びとは大きく異なります。大学では「教えてもらう」のではなく「自ら学ぶ」という姿勢が必要であるという点も意識しておく必要があります。「自主的、主体的に実社会で利用できる知識、技術を修得する」、これが「工学部における学び」なのです。自由度が高く、目的をしっかり持っていれば、様々なことができる面白味があります。
自分が作り出した”モノ”あるいは”環境”で人々の生活を豊かにできるかもしれないと考えると、ワクワクしませんか?工学部で学び、ぜひそのワクワク感を体験してください。
 日本最古の現役鉄製道路橋「出島橋」(1890年架設,1910年移設)
日本最古の現役鉄製道路橋「出島橋」(1890年架設,1910年移設) | 掲載大学 学部 |
長崎大学 工学部 | 長崎大学 工学部のページへ>> |
関連記事
(>>会員用ページ)
| 私たちが考える未来/地球を救う科学技術の定義 | 現在、環境問題や枯渇資源問題など、さまざまな問題に直面しています。 これまでもわたしたちの生活を身近に支えてきた”工学” が、これから直面する問題を解決するために重要な役割を担っていると考えます。 |